倉工電通3期会 〜皇居東御苑他散策〜
先ずは、
皇居東御苑散策→楠正成像を観て→楠公レストランハウスで昼食。
その後、新橋に移動して、電通本社ビルの46階から東京湾を展望する。そして、浜離宮恩賜庭園を散策→水上バスで、浅草へ。浅草寺をお参りして、浅草「うなぎ小柳」で小宴会。お土産に神谷バーで、デンキブランを買って解散した。移動範囲は、マップを参照願います。
マップ
より大きな地図で 皇居東御苑他散策 を表示
電通本社ビル46階で展望
皇居東御苑を散策後、楠正成像を観て、浜離宮恩賜庭園を散策するために新橋に移動した。幹事役のTA氏は、東京湾を一望できるビルがあるので、そこに寄ってから浜離宮に行こう。といって我々を先導した。そのビルは電通本社ビルの46階で、浜離宮や築地市場、レインボーブリッジを眺めることができた。
| 電通本社ビル46階に上る |
| 浜離宮恩賜庭園の全景 |
| 築地市場 |
| 前方はレインボーブリジヂ |
| これは亀の噴水です |
浜離宮恩賜庭園
海水を引き入れた潮入の池と、ふ たつの鴨場を伝え、江戸時代には、 江戸城の「出城」としての機能を果 たしていた徳川将軍家の庭園です。 承応3(1654)年、徳川将軍家の鷹狩
場に、四代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が、海を埋め立てて甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を建てました。その後、綱重の子、綱豊(家宣)が六代将軍になったのを契機に、この屋
敷は将軍家の別邸となり、「浜御殿」と呼ばれるようになりました。以来、歴代将軍によって幾度かの造園と改修工事が行われ、十一代将軍家斉の時代にほぼ乳在の姿の庭園が完成しました。明治維新ののちは皇室の離宮となり、名称を「浜
離宮」と変えました。関東大震災や戦災によって、御茶屋など数々の建造物や樹木が損傷し、往時の面影はなくなりましたが、昭和20(1945)年11月3日、東京都に下賜され、整備ののちに昭和21(1946)年4月から公開されました。その後、昭和27(1952)年11月22日に国の特別名勝及び特別史跡に指定されました(指定管理者(財)東京都公園協会 文化財庭園チームの資料から)。
先ずは、園内マップをご覧ください(「公園に行こう」のページから)。
園内マップ
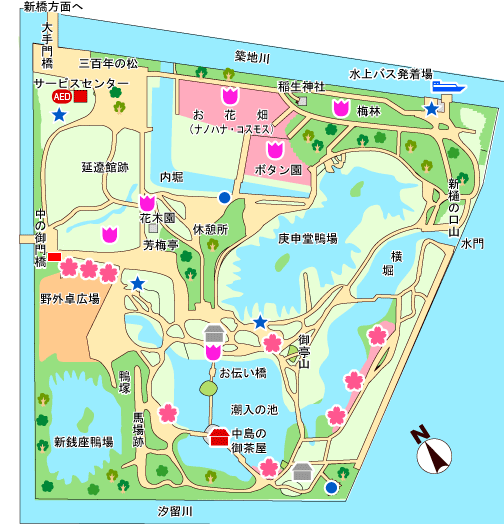 |
三百年の松
およそ300円前の宝永6年(1709) 6代将軍徳川家宣がこの庭園を大改修した(そのときから「浜御殿」と改称された)ときに植えられたと伝えられており、 その偉業を表現するような雄姿は昔時をしのばせるもので、都内では最大級の黒松であります(説明版より)。
| 黒松の念力を頂きます(300年の松をバックに) |
ボタン園とお花畑
ぼたん園は60種約800株が植えられており、春にはとりどりの花が優雅さを競っています。お花畑では、春は「ナノハナ」、秋には「キバナコスモス」が美しく咲き誇ります(指定管理者(財)東京都公園協会 文化財庭園チームの資料から)。
| 見ごたえのあるナノハナです。前方右のビルが電通本社ビル |
旧稲生神社
旧稲生神社の創建時期は明らかではありませんが、江戸時代に後期の得ずには現在の場所より西方に稲荷社が描かれていることから 庭園内に稲荷社が古くから祭られていたことが知られています。
現在の建物は、前身となる社殿が明治27年(1894)6月20日に 東京湾を震源とする地震で倒壊したため、翌年に当時の宮内省内匠寮の手によって、同規模・同形式で再建されたものです。 一方、内部に祭れれている宮殿は、その建築技法から江戸時代後期のものであると推定されます。
建立から現在に至るまで、 幾度か修理の手が加えられたことが、調査によって判明しています。なかでも、対象12年(1923)9月1日に発生した関東大震災
では大きく破損し、倒壊は免れたようですが、昭和6年(1931)に同じく内匠寮によって大修理が行われました。 そして、平成17年には文化財としての大掛かりな修理を行い、ここに明治時代の創建当時の姿を伝えています(説明版より)。
| 明治時代の創建当時の姿を伝えてる旧稲生神社 |
御亭山
御亭山(おちんやま)と読みます。西には富士山、北に江戸城、北東に筑波山、東から南にかけて江戸湾・白帆、 その向こうの南には房総半島が横たわり、360度の眺望が楽しめました。 また、池に目を移せば、御伝い橋が、鶴が今まさに飛びたたんとする姿にみえます。と説明されているようです。 (「趣味はモーニング食べ歩き♪」ページより)。
| 御亭山(おちんやま) |
| 前方が中島のお茶屋(鶴が今まさに飛びたたんとする姿にみえますか?) |
水上バス発着場
「浅草」「両国」「お台場海浜公園」、および「葛西臨海公園」「桜橋」等への発着場です。隅田川に架かる個性豊かな14の橋を楽しむことができます(指定管理者(財)東京都公園協会 文化財庭園チームの資料から)。
こんな大きな船が、隅田川を行き来するなど知らなかった。
| 隅田川に架かる個性豊かな橋を数えよう |
| 船内の様子、天井展望できます |
| 今度は、屋形船に乗ろう |
| 松本零士氏がデザインした新型水上バスヒコミに乗りたい |
| もう300メートも出来ている東京スカイツリータワー、あとこの倍だ |
浅草寺
水上バスは、吾妻橋をくぐり、言門橋と桜橋をくぐったところで、Uターンして終点の吾妻橋で下船した。
浅草寺にお参りに行く途中に、幹事役のTA氏が、創業明治13年の神谷バーがあるので、寄って行こうと言ったが1時間待ちだったので、諦めてそのまま浅草寺にいった。浅草寺本堂は、改修工事で、全体が白幕で包まれていた。
| 雷門の前で |
| 宝蔵門(戦前は仁王門といいました) |
五重塔
そもそも仏塔とは、遠くインドで釈尊の遺骨(仏舎利)を起塔供養したのがはじまり。アジア東漸を経て、さまざまな形となった。五重塔もその一形態。
浅草寺五重塔は、天慶5年(942)、平公雅によって創建されたのをはじめとする。その後、数度倒壊に遭うも、その都度再建された。徳川家光によって再建された国宝五重塔も、昭和20年3月の戦災によって惜しくも焼失した。(戦前までの五重塔は、今と反対側の本堂に向かって右側にあった)
以来、浅草寺は十方各位のご信助を得て、また新たにスリランカ国の王位寺院より「聖仏舎利」を勧請(五重塔最上層に奉安)し、昭和48年に、現在の五重塔を再建するに至った。
地上からの高さは53メートルある。(塔内非公開)(説明版より)
| 五重塔(戦前までは、本堂に向かって右側にあった) |
一応、本日の予定のコースを廻ったので、浅草公会堂の近くにある、うなぎ「小柳」で小宴会をした。ここの蒲焼はうまかった。 帰りに、もう一度神谷バーに寄ったが、やはり満席だったので、お土産に「デンキブラン」を買った。
| 小柳の店の前で |
| 神谷バーがある通り、この先に雷門がある |
今回は東京近辺の散策であったが、皇居東御苑と隅田川水上バスは、初めてだったので大変有意義な一日でした。幹事役のTA殿、ご苦労様でした。次回は何処にいきましょうか?
このページのTOPへ前のページへ