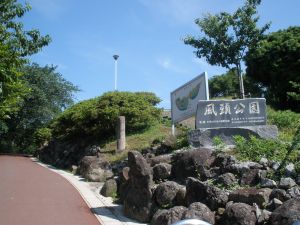先ずは、路面電車で「思案橋」で下車、史跡 花月を散策、崇福寺、風頭公園、龍馬像、亀山社中の跡を観光する。
マップ
観光した場所をポイントしています。ご覧ください。
より大きな地図で 長崎 を表示
料亭 花月
「花月」は寛永19年(1642年)に創業した遊女屋引田屋(ひけたや)の庭園内に造られた茶屋の名前です。昭和35年には長崎県の史跡に指定されて、全国的に珍しい史跡料亭となりました。
「竜の間」の床柱には、坂本龍馬がつけた刀傷の跡が生々しく残っています。(長崎味彩記 史跡料亭 花月 サイトより)近くに丸山公園があり、龍馬の像があるが、男前に造られている。
 |
 |
| 史跡 花月 |
花月の入口 |
崇福治
寛永6年(1629年) 長崎で貿易を行っていた福建省出身の華僑の人々が、福州から超然を招聘して創建。中国様式の寺院としては日本最古のものである。福建省の出身者が門信徒に多いため福州寺と称せられた。
(崇福治-長崎市 Wikipedia サイトより)拝観料:300円と表示されていたが、無料で入れた。
 |
 |
| 三門 |
第一峰門(国宝) |
幣振坂
説明版によると、「幣振坂の名前は、寛永11年(1634)、諏訪神社の一の鳥居に使用するための石材を麓に卸した際、宰領が御幣(紙を切り細長い木に挟んで垂らした神祭用具)を振って、人夫達を鼓舞したことに由来するとも言われています。この坂は、長崎ロケが行われた映画「解夏(げげ)」の冒頭やラストシーンに出てきます。」とある。この坂を延々と上って行く。途中からまわりが墓地になる。シーボルトゆかりの人たちの顕彰碑や楠本の家の墓があった。
 |
 |
| 幣振坂上って行く! |
シーボルトゆかりの人たちの顕彰碑 |
なお、上って行くと風頭公園の入口が見えてきた。入口の前に長崎凧資料館があったので、覗いて見た。結構有名人が来ているらしく、写真が飾ってあった。
風頭(かざがしら)公園入口と凧館(ハタやかん)
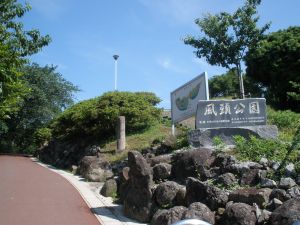 |
 |
| 風頭公園の入口 |
凧館(ハタヤかん) |
龍馬像に行く間に、上野彦馬の墓があった。
上野彦馬の墓
上野彦馬は幕末の長崎が生んだ我が国写真技術の始祖であり彦馬が移した坂本龍馬や桂小五郎などの写真はあまりにも有名であります。幕末維新 動乱時代に借行写真家として苦難の道を切り開いた彦馬の生涯と偉大な業績が日本写真発展の基礎となって生きつづけています。 と刻まれている。
|
 |
龍馬像
亀山社中の跡
龍馬像から龍馬通りを通って、亀山社中の跡に行く。慶応元(1865年)5月に、坂本龍馬(1835年〜1867年)は、この地に日本で初の商社を設立し「亀山社中」と称しました。亀山社中の事業は航海・海運・貿易などでした。慶応3年(1867年)4月、亀山社中は土佐藩直属の海援隊となり、坂本龍馬は隊長に任命されました。坂本龍馬は周知のとおり幕末における風雲児として東奔西走、維新の原動力となって神戸海軍操練所の設立、亀山社中の設立、薩長連合の周施と大政奉還への大一人者として実践行動力の人となり日本の基礎を築き、33才の青春を燃焼しつくした先達の人です。なお幕末期の名窯亀山焼きの窯跡は50m程上方、現在の平公民館の場所になります。また近く「竹の芸」で有名な若宮稲荷神社があり、市民の憩いの場として親しまれています。(亀山社中ば活かす会の看板より)入場料:300円。
 |
 |
| 龍馬通り |
亀山社中の跡 |
 |
 |
| 坂本家の家紋が入った黒地羽二重の紋服 |
当時のメンバー |
このページのTop へ
次は、龍馬のブーツ像・亀山社中資料展示場・若宮稲荷神社・眼鏡橋・新地中華街・長崎空港 へ
(旅行日 2011.05.26〜30)